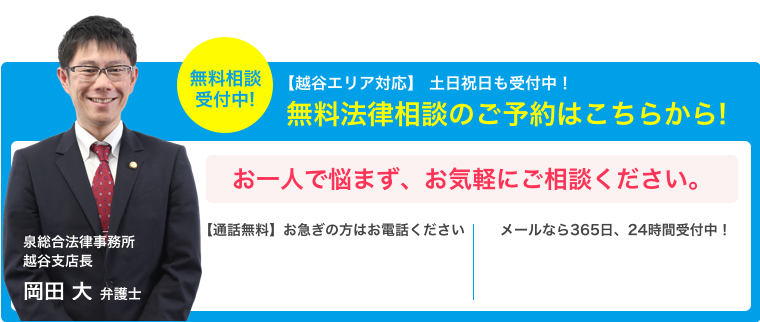後遺障害等級に認定されない!非該当の場合の対処法

- 交通事故で後遺障害に認定されなかった!
- 明らかに痛みが残っているのに「非該当」になってしまった
- 後遺障害の認定結果に異議申立てをしたい
交通事故で痛みやしびれ、関節の可動域制限など、様々な後遺症が残っても、後遺障害として認定を受けられない(非該当になる)ケースがあります。
その場合でも「異議申立て」を行うことにより、後遺障害認定される可能性があるので、諦める必要はありません。
以下では、後遺障害等級に認定されなかった場合の「異議申立て」方法について、弁護士が解説していきます。
このコラムの目次
1.後遺障害認定に対する「異議申立て」
交通事故で症状固定時に何らかの後遺症が残ったら、自賠責保険に対して後遺障害認定請求をします。
ここで1~14級のいずれかの等級に認定されたら、認定された等級に応じた慰謝料や逸失利益が支払われます。
しかし、場合によっては、症状が残っているにもかかわらず等級認定されないケースがあります。
後遺障害の立証が不十分であった場合や、交通事故と症状との因果関係が否定されてしまうことなどが原因です。
このように、後遺障害を否定されることを「非該当」と言います。
その場合、後遺障害に関する補償は行われません。
非該当になって納得できない場合、「異議申立て」をすると認定結果を覆せる可能性があります。
後遺障害認定に対する異議申立てとは、自賠責保険に対して再度後遺障害についての審査を要求する手続きです。
申立先は、一度目に等級認定請求をしたのと同じ「自賠責保険」です。
異議申立てには特に「期間制限」はありません。保険金請求権の時効が成立するか示談が成立するまでいつでも申立て可能です。
また回数にも制限がなく、納得できないなら何度でも異議申立てできます。
ただし、異議申立て先は「同じ自賠責保険」ですから、同じ方法で異議申立てを何度繰り返しても、認定結果が覆る可能性は極めて低いです。
異議申立てを成功させるには、1回目の失敗原因を踏まえて別の資料等を揃え、綿密に計画立てて進める必要があります。
2.異議申立てを検討すべきケース
後遺障害認定結果が出たときに異議申立てを検討すべきケースは、以下の2種類です。
(1) 非該当になった(認定されなかった)
「そもそも後遺障害が残っていない」と判定されるケースです。
むちうちで他覚所見がない(MRIなどに異常所見が見当たらない)場合などに非該当になるケースが多くなっています。
非該当になると、後遺障害が残っていない前提なので、慰謝料も逸失利益も一切支払われないこととなります。
不服があるなら異議申立てを行って、「後遺障害」として認定を受ける必要があります。
(2) 予想していた等級より低くなってしまった
もう1つは、等級認定されたけれども思ったより低くなってしまったケースです。
たとえば、被害者としては5級相当だと思って認定請求をしたけれど9級になってしまった場合などには、9級相当の慰謝料と逸失利益しか支払われないので、賠償金が大幅に低くなってしまいます。
この場合にも異議申立てを行い、より高い等級に変更してもらうメリットがあります。
3.異議申立ての手順
後遺障害認定結果に不満がある場合、具体的にはどのようにして異議申立てをすればよいのでしょうか?
(1) 「異議申立書」を提出する
異議申立てを行うときには、基本的に「異議申立書」を自賠責保険に提出します。
異議申立書では、「一度目の決定内容にどの点に不満があるのか」「なぜ等級認定すべきと言えるのか」を説得的に論証する必要があります。
(2) 資料を提出する
異議申立てによって実際に認定結果を覆すには「異議申立書」の提出だけでは足りません。
資料がなければ結局は一度目と同じ認定になってしまいます。
具体的には新たな診断書などの資料が必要です。後遺障害診断書や新たな検査を行った結果の資料、医師の意見書などをつけて提出しましょう。
4.異議申立ての2種類の方法
異議申立てには2種類の方法があります。どちらを選択するかによっても認定結果が覆るかどうかも変わってくるので、是非とも押さえておいてください。
(1) 事前認定
「事前認定」は、相手の「任意保険会社」に後遺障害認定を任せる方法です。
もともと事前認定で後遺障害申請をした場合、異議申立てするときにも引き続いて事前認定で進めることが多くなっています。
事前認定ではすべての対応を任意保険会社の担当者に任せてしまうので、どのような手続きが行われているかが見えにくいです。
相手がきちんと対応してくれているかどうかわかりませんし、被害者が自ら積極的に異議理由を述べたり立証したりすることも難しくなります。
後遺障害認定されるか微妙な事案で異議申立てをするなら、事前認定はお勧めではありません。
(2) 被害者請求
「被害者請求」とは、被害者自身が自賠責保険に対して後遺障害認定申請をする方法です。
一度目に被害者請求した場合には異議申立ての際にも被害者請求となります。
また一度目に事前認定を利用した場合にも、異議申立ての際には被害者請求に切り替えることが可能です。
被害者請求をするときには、被害者自身が多くの書類や資料を集めたり損害保険料算出機構などと連絡をとったりしなければならないので手間がかかります。
ただ、積極的に主張や立証ができるので、1回目に非該当とされた場合などにはこちらの方が有効です。
被害者請求をするときには、事前認定とは異なりいろいろな書類が必要です。
一度目に被害者請求をした場合には異議申立ての際に同じ書類を省略できますが、1度目が事前認定で異議申立ての際に被害者請求に切り替えるには、あらためて以下のような書類が必要です。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 交通費明細書
- 休業損害証明書
- レントゲンやMRIなどの検査記録
また、被害者請求の場合、上記にとどまらず被害者にとって有利な内容の意見書を医師に作成してもらって提出することなども可能です。
(3) 事前認定と被害者請求の選び方
事前認定では異議申立書を相手の保険会社に渡すだけで済むので簡単ですが、それでは非該当の判定を覆すことが困難となるでしょう。
異議申立てを成功させたいなら、被害者請求を利用することを強くお勧めします。
5.異議申立てを成功させるポイント
後遺障害非該当となった場合、異議申立てを成功させるには以下のようなことが重要です。
(1) 敗因を分析する
まずは1度目の後遺障害認定でなぜ非該当となったのか、あるいは等級が低くなってしまったのか、分析しましょう。
症状の立証が不足していたのか、因果関係が否定されたのか、既往症が影響したのかなど、原因によって対処方法が異なります。
後遺障害の認定通知書に書かれている理由が不十分な場合には、より詳細な理由の開示を求めることも可能です。
(2) 医学的な資料を用意する
次に、後遺障害の認定結果を覆せるだけの医学的な資料を集める必要があります。
後遺障害認定されない場合、多くのケースでは「症状の立証が足りていない」からです。
たとえばMRI以外には何の資料も提出されていない場合、後遺障害診断書に書かれている内容が不足している場合などがあります。
そういった場合、他の検査を行ってその報告書を提出したり、医師に再度後遺障害診断書を書き直してもらって提出し直したりしましょう。
医師に「意見書」という形で難しい症状についての見解を説明してもらい、後遺障害認定の資料とすることもできますし、医学的な文献や論文等の資料をつける方法なども考えられます。
(3) 説得的な異議申立理由を述べる
異議申立書の書き方にも注意が必要です。
単に「痛みが続いている」「日常生活に支障が出ている」「仕事を辞めた」などの事情を書いただけでは後遺障害認定は覆りません。
「どんな症状があるのか」「その症状が交通事故によって発生したと言えるのか」「症状が後遺障害認定基準に該当すると言える理由」を説得的に書かねばなりません。
自分でうまく文章化できない場合には、弁護士に依頼して異議申立書を作成しましょう。
6.異議申立ては弁護士までご依頼ください
異議申立てを成功させるには、医学的な知識も必要ですし、医師とのやり取り、効果的な異議申立書の作成など、さまざまな対応を要求されます。
被害者お一人で進めるより、弁護士に依頼した方が、格段に成功率が上がります。
後遺障害が認定されず不満を抱えておられるなら、泣き寝入りせずにどうぞ泉総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
-
2019年3月25日交通事故 交通事故の損害賠償で重要な書類
-
2019年8月6日交通事故 後遺障害認定手続きは「被害者請求」が良いって本当?
-
2020年1月29日交通事故 埼玉県越谷市で交通事故に遭った場合にするべきこと